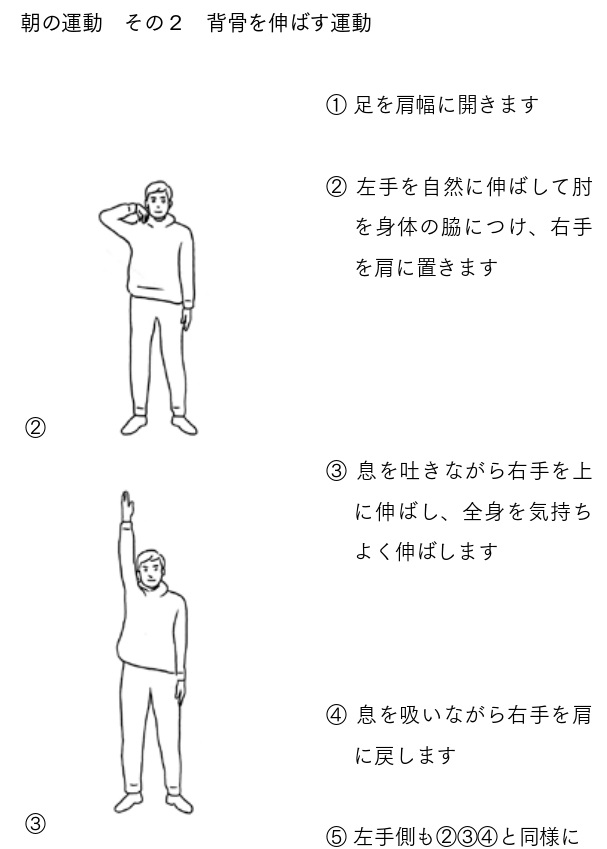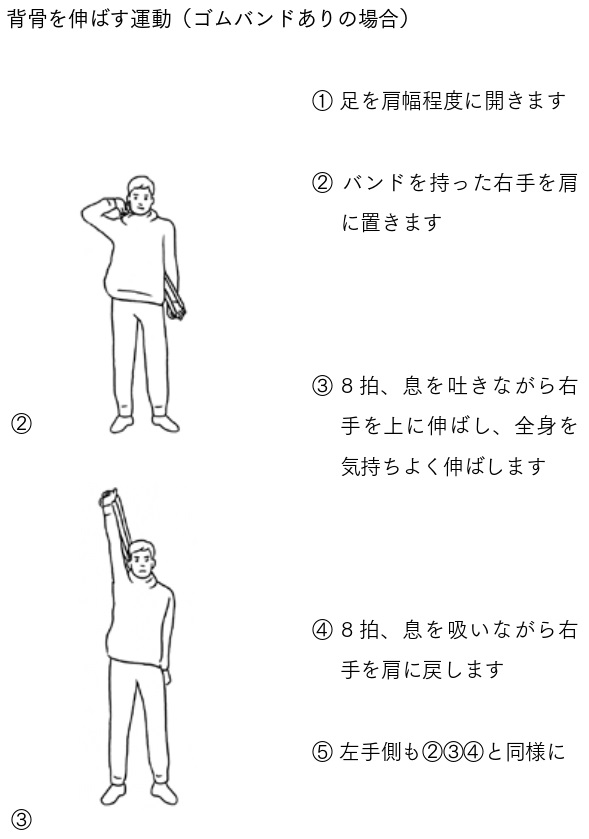凹んだら読む本_第三章(17)
国際メンタルセラピスト協会 HOME > 凹んだら読む本
17.寝る前1時間は「パソコンや スマートフォン」から離れる!

電子機器の液晶ディスプレイから出る青い光は、 睡眠の質を低下させてしまう
凹んだときは、「誰とも会いたくないなぁ」と感じることもあると思います。
そんなとき、一人でパソコンやスマートフォンでネットサーフィンをしたり、
友達にメールをしたりすることもあるでしょう。
ただ、寝る直前までパソコンやスマートフォンを見ていると、なかなか眠れないことはありませんか。
この「寝る前のスマートフォンいじり」は、睡眠の質を低下させて、身体に悪影響をもたらします。
人間が規則正しいサイクルで睡眠と覚醒を行えるのは「メラトニン」というホルモンのおかげです。
しかし、テレビやパソコン、スマートフォンやタブレットなどの光を夜間に浴びると、
このホルモンの分泌量が抑えられてしまいます。
そのため睡眠のサイクルが崩れ、眠りが浅くなったり、寝つきが悪くなったりという症状が表れます。
メラトニンは体温・脈拍数・血圧などを下げる働きがあり、身体を休息・睡眠へと誘う物質です。
つまり、このホルモンが増えれば眠くなり、減れば目が覚めるということ。
メラトニンは強い光を浴びると分泌されにくくなり、逆に暗い場所にいると分泌量が増加するので、
人間は夜に眠くなるわけです。
しかし、日中に太陽の光を浴びない生活が続いたり、夜に強い光を見たりしていると、
メラトニンの「昼に減り、夜に分泌される」という規則性に狂いが生じて、
夜になってもスムーズに眠りに入ることができなくなるのです。
とくに真昼の空と同じ青色の光を見ていると、本能的に「いまは昼だ」と感じてしまい、
メラトニンの分泌量が落ちやすくなるといわれています。
スマートフォンなど、多くの電子機器のディスプレイに使われている発光ダイオード(LED)が放つ青い光「ブルーライト」は、
とくにメラトニン抑制を助長するといわれています。
また、寝る前の暗い部屋の中で目に受けるブルーライトは、睡眠障害につながるだけでなく目への負担も大きく、
目の疲れ、目の痛み、網膜へのダメージなども同時に引き起こすといいます。
さらに、画面に表示される情報を読んでいることでも、脳が活性化されて覚醒状態になってしまいます。
ブルーライトは、細かくいえば波長が380~495ナノメートル前後の紫色から青色の光で、
人間が目で見ることのできる光(可視光線)の中でもいちばん波長が短い部類に入り、エネルギーが強く、
目の中の角膜や水晶体で吸収されずに網膜までダイレクトに届いてしまうといわれています。
いまや私たちの日常にあふれているブルーライト。
しかしこの波長の光は、私たちの身体にダメージを与えてしまうのです。
このように、寝る前にスマートフォンを見ていると、メラトニンの分泌が抑えられて寝つけなくなり、
夜型生活になってしまいやすいのです。
さらに、これが悪化すると、不眠症にも陥りかねません。
就寝までの2時間以内にスマートフォンやパソコンをいじっていると、睡眠に悪影響が出るという研究もあり、
身体の不調や睡眠障害を感じている方は、寝る前にこうした電子機器を使わないことがいちばんの改善策だといえます。
いまや「起きてから寝るまでスマートフォンが手元にないと落ち着かない」というへビーユーザーも多いと思いますが、
寝る1時間前からは電子機器を使わないだけでも、睡眠状態の改善が望めるという医師もいます。
まずは「就寝1時間前にはスマートフォンから離れる」ということから始めてみましょう。
凹んだときは、「誰とも会いたくないなぁ」と感じることもあると思います。
そんなとき、一人でパソコンやスマートフォンでネットサーフィンをしたり、
友達にメールをしたりすることもあるでしょう。
ただ、寝る直前までパソコンやスマートフォンを見ていると、なかなか眠れないことはありませんか。
この「寝る前のスマートフォンいじり」は、睡眠の質を低下させて、身体に悪影響をもたらします。
人間が規則正しいサイクルで睡眠と覚醒を行えるのは「メラトニン」というホルモンのおかげです。
しかし、テレビやパソコン、スマートフォンやタブレットなどの光を夜間に浴びると、
このホルモンの分泌量が抑えられてしまいます。
そのため睡眠のサイクルが崩れ、眠りが浅くなったり、寝つきが悪くなったりという症状が表れます。
メラトニンは体温・脈拍数・血圧などを下げる働きがあり、身体を休息・睡眠へと誘う物質です。
つまり、このホルモンが増えれば眠くなり、減れば目が覚めるということ。
メラトニンは強い光を浴びると分泌されにくくなり、逆に暗い場所にいると分泌量が増加するので、
人間は夜に眠くなるわけです。
しかし、日中に太陽の光を浴びない生活が続いたり、夜に強い光を見たりしていると、
メラトニンの「昼に減り、夜に分泌される」という規則性に狂いが生じて、
夜になってもスムーズに眠りに入ることができなくなるのです。
とくに真昼の空と同じ青色の光を見ていると、本能的に「いまは昼だ」と感じてしまい、
メラトニンの分泌量が落ちやすくなるといわれています。
スマートフォンなど、多くの電子機器のディスプレイに使われている発光ダイオード(LED)が放つ青い光「ブルーライト」は、
とくにメラトニン抑制を助長するといわれています。
また、寝る前の暗い部屋の中で目に受けるブルーライトは、睡眠障害につながるだけでなく目への負担も大きく、
目の疲れ、目の痛み、網膜へのダメージなども同時に引き起こすといいます。
さらに、画面に表示される情報を読んでいることでも、脳が活性化されて覚醒状態になってしまいます。
ブルーライトは、細かくいえば波長が380~495ナノメートル前後の紫色から青色の光で、
人間が目で見ることのできる光(可視光線)の中でもいちばん波長が短い部類に入り、エネルギーが強く、
目の中の角膜や水晶体で吸収されずに網膜までダイレクトに届いてしまうといわれています。
いまや私たちの日常にあふれているブルーライト。
しかしこの波長の光は、私たちの身体にダメージを与えてしまうのです。
このように、寝る前にスマートフォンを見ていると、メラトニンの分泌が抑えられて寝つけなくなり、
夜型生活になってしまいやすいのです。
さらに、これが悪化すると、不眠症にも陥りかねません。
就寝までの2時間以内にスマートフォンやパソコンをいじっていると、睡眠に悪影響が出るという研究もあり、
身体の不調や睡眠障害を感じている方は、寝る前にこうした電子機器を使わないことがいちばんの改善策だといえます。
いまや「起きてから寝るまでスマートフォンが手元にないと落ち着かない」というへビーユーザーも多いと思いますが、
寝る1時間前からは電子機器を使わないだけでも、睡眠状態の改善が望めるという医師もいます。
まずは「就寝1時間前にはスマートフォンから離れる」ということから始めてみましょう。
リンパ系ホルモン系の働きをコントロールし、自律神経と深く関わっています。ストレス気味のと き、凹んだときにはぜひ刺激してみてください。
小指には「心経」と「小腸経」の2本の経絡が通っています。心経は心臓と血液循環器 に関連する経絡です。心経の始点のツボは、爪の薬指寄り生え際にある「少衝」です。小 腸経は小腸の働きをコントロールする経絡です。小腸経の始点は、小指の爪の外側の生え 際にある「少沢」です。
このように、各指の爪の生え際には、私たちの各臓器をコントロールするッボがあり、
疲れたときには、腹式呼吸をしながら、各指の爪の生え際を人差し指と親指で刺激をする
ことで、頭をすっきりさせることができます。 ツボ押しは、通勤中や休憩時間などに簡単に行えます。一つひとつのツボの効果を確認
しながら刺激することも大切ですが、そんなに難しく考えなくても、ちょっと疲れたら、
手の指の爪の生え際を刺激すると、元気になれます。私自身もよく電車の中で、指の爪の
生え際を刺激しています。
小指には「心経」と「小腸経」の2本の経絡が通っています。心経は心臓と血液循環器 に関連する経絡です。心経の始点のツボは、爪の薬指寄り生え際にある「少衝」です。小 腸経は小腸の働きをコントロールする経絡です。小腸経の始点は、小指の爪の外側の生え 際にある「少沢」です。
このように、各指の爪の生え際には、私たちの各臓器をコントロールするッボがあり、
疲れたときには、腹式呼吸をしながら、各指の爪の生え際を人差し指と親指で刺激をする
ことで、頭をすっきりさせることができます。 ツボ押しは、通勤中や休憩時間などに簡単に行えます。一つひとつのツボの効果を確認
しながら刺激することも大切ですが、そんなに難しく考えなくても、ちょっと疲れたら、
手の指の爪の生え際を刺激すると、元気になれます。私自身もよく電車の中で、指の爪の
生え際を刺激しています。